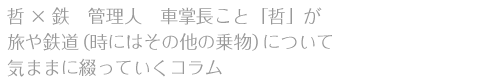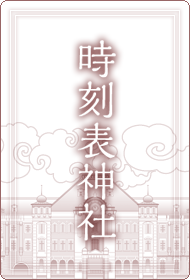湯るり揺られ緩みっぱなしの旅
カテゴリー:①番線:鉄道(JR・私鉄)方面 2014年9月29日 04:46
これで直江津を通ったのは5回目…
直江津駅は新潟県上越地方の交通の要衝であり、JR東日本と西日本の境界点でもある。
現在は金沢・富山などの北陸方面と、首都圏ならびに新潟圏を結ぶ特急列車が頻繁に行き交い、ホームでは駅弁を売る姿も見受けられ、人の往来の多さを物語っている。
しかしながら、そんな光景も来春の北陸新幹線開業で様変わりしてしまうだろう…
9月最後の週末、車掌長が所属する温泉達人会の分科会「鉄&温泉委員会」主催の旅に参加した。
泉質の分析表とは別の「鉄分」が多い同好者の集まりで、年2回さまざまなテーマで鉄分を体内に補充している。
今回は、北陸新幹線開業で消えてゆくものを訪ねては、現風景を記録や記憶に残しつつ、沿線の湯も楽しむ旅となった。
全てを書き記すことは締りがなくなるので遠慮しておくが、訪れた箇所を列記しておきたい。
(鉄道関係)
①北越急行ほくほく線「はくたか」乗車と「美佐島駅」探訪
②北陸本線「筒石駅」探訪
③信越本線普通列車「妙高」乗車
⑤「二本木駅」スイッチバック
⑥「脇野田駅」駅舎と「上越妙高駅」
⑦快速「くびきの」乗車
⑧直江津駅弁調整元ハイマートの「鱈めし」ほか
(温泉)
①門前の湯(直江津)
②燕温泉(河原の湯、黄金の湯、宿泊先の湯)
③寺宝温泉(長岡)
④西谷温泉(長岡)
⑤糸魚川温泉
と、このような箇所を鉄道を使って1泊2日で周ってきた。
この場で個々の列車や駅、温泉などの印象や感想は、またの機会としておきたい。
おそらく、名称を見ただけではどのような場所か想像がつかない方が多いと思う。
お手数をかけて大変恐縮ではあるが、ぜひネット検索等で追体験をしていただければ幸いだ。
それにしても、2日間好天に恵まれ気分も良く、列車に乗るごと、温泉に入るごとに、ビールや酒を飲む12名の一行が、緻密なスケジュールを消化できたことは良かった。
これもT委員長をはじめ同行者の一糸乱れぬ(!?)行動と意識の現れか…ということにしておこう。
この場を借りて、T委員長の各方面へのご尽力と、参加された同好・同行の皆様、そして何よりも毎度このような旅に出張許可を出してくださる専務車掌に、心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました
こころを読み終えて
カテゴリー:④番線:日々雑感方面 2014年9月25日 05:39
子ども時代の読書感想文のようなタイトルが懐かしい。
本日付で朝日新聞に連載されてきた「こころ」が終着駅に到着した。
そのホームに降り立った車掌長の心情は、明治という1つの時代の終焉が、漱石自身の「何か」の区切りでもあったというものだ。
それを、「私」であったり、「先生」であったり、「K」という友人に、自身の思いの丈(たけ)を代弁させたのであろう。
今回の「こころ」の連載は、1914年(大正3)4月20日から8月11日まで、当時の朝日新聞に連載されてからちょうど百年を迎えたことを記念し、時同じくして本年4月20日から再度連載されたもの。
毎朝、紙面を順番に読み進めて、読者の「声」や社説と同じ頁にあるこの連載小説に辿り着く頃には、飲み始めたコーヒーが半分ほどになっていたものだ。
連載が始まった頃、新聞に目を通す頃は夜が明け始め、コーヒーもアイスであったが、最近はまだ夜も明けず、つい先日からはホットに変わり、季節が移ろいだのを感じた矢先でもあった。
明治という時代が、どのような世の中であったり、人々の精神的な生き様を、少し垣間見れたような心持ちになった。
一方、自分自身に置き換えてみると、「昭和」という時代から「平成」という時代を、40代後半という歳で生きている意味を、ふと感じてしまった。
過ぎた時間は輝きを増して回顧されるというが、不便だったことや、不幸な出来事も含めて、「昭和」の頃は良かった…などと、感慨に耽ってしまうのは早計だろうか…
しかも、「昭和」とは言っても、車掌長は戦争という暗黒な時代を知らない世代。
世の中が経済的に発展し、多くの人々が自由を享受、謳歌する「昭和」を、子どもから学生時代まで過ごした。
このたび、「こころ」が終着駅に着いたところで、車掌長自身の「昭和」にも、何か区切りをつけねばならない…という心情になった。
なんとも、とりとめのない中途半端な感想だが、率直な想いでもある…
うなぎ弁当の思ひで
カテゴリー:③番線:時間旅行、時刻表方面 2014年9月19日 04:53
駅弁を食べるなら、列車が動き出してからに限る。
乗車列車が途中駅なら、ごく当たり前のことかもしれないが、始発駅の場合は出発前に食べ終えてしまう人も見かける。
もちろん、駅弁をいつ食べねばならぬという決まりはなく、各自の自由な裁量の範囲の話…
しかしながら、列車が動き出してからの方が、「流れる車窓」も視覚的な味わいとなるし、揺れる中で箸を進めるのが列車の旅の醍醐味なのだと思う。
車掌長が駅弁の中で大好きなものの1つが、「うなぎ弁当」。
一番最初にうなぎ弁当を食べたのは、小学5年生の時の一人旅で、新幹線の車内だった。
その頃の一人旅の食事は、朝や昼は150円前後の駅の立ち食いそばで、夕食は300円ほどの助六ずしが定番であったが、その時はさらに切り詰めて、念願の「うなぎ弁当」を食べたいと思った。
そして、初のうなぎ弁当は、車掌長なりに食べるイメージを考えて臨んだ。
上りの東海道新幹線で、浜名湖辺りで車内販売のお姉さんから購入し、富士山を見ながら食べる…それも長く乗っていられる「こだま号」で。
しかも、食後の「シメ」は好物だった冷凍ミカンも…と欲を張ったが、1人で5個は食べられないので断念した。
当時の記憶では、うなぎ弁当は700~800円だったが、浜松駅や新幹線車内では、更に1200~1300円のいわゆる「上」があった。
もちろん、捻出したお金で買えるのは「並」であったが、2名掛けのE席から富士山を眺めて食す「うなぎ弁当」は、格別の満足感に浸ることができた。
あれから約35年が経ち、うなぎ弁当の値段は捻出どころでは味わえない、車掌長にとっては幻の駅弁になってしまった…
手元にある直近のJTB時刻表を見ると、東京駅で売っている「国産うなぎ弁当」が2250円。浜松駅では「濵松うなぎ飯」が2780円だ。
ところで、今年6月に、ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されたことは、まだ記憶に新しい。
また、つい先日は養殖量そのものを削減することで、日本・中国・台湾・韓国が合意し、ニホンウナギの資源管理が国際的に整備されることになった。
そうした背景を考えれば、今後ますます、うなぎ弁当の値段は高騰すると思われる。
日本は世界のウナギ消費量のおよそ7割を占めるというが、今まで無秩序に食べ過ぎてきたことが、絶滅危惧への警鐘を鳴らしたのであろう。
もはや街中でも、手軽に食べられなくなったウナギだが、日本の食文化を維持継承するためにも、我慢しなければならない。
さて、今度はどんな「ハレ」の日に食せるか、その時を楽しみにしていたい。
どこにいだの みんなまってるよ!
カテゴリー:④番線:日々雑感方面 2014年9月13日 05:28
「みなさんは いま そういう場所に立っているんです」
大槌町の旧役場庁舎の玄関前、黙祷を捧げた後に、語り部ガイドの東梅さんがそう切り出した。
庁舎の時計は、津波に襲われた時刻を指したまま…
そこから、町の時間も止まったまま…
8月下旬、母の看護学校時代の同窓旅行を企画・手配・添乗し、青森や岩手を訪れた。
その際、通常の観光以外に、東日本大震災で被災した地域を訪ねたいと考えた。
それは、震災から3年半が経過し、自分自身も含めた社会全体に、「あの日」の記憶が薄らいだり、風化しつつある懸念や危機感があったことに他ならなかった。
計画当初は、車で被災地を回り、今も生々しく時を止めた遺構を見るだけでも、「何か」を感じられるとプランニングをしていた。
だが、それでいいのか…?と、違和感を抱くようになった。
そして、更に下調べをしてゆく中で、被災した町民の方が語り部となり、「あの日」を自身の言葉で案内してくれる団体の存在を知った。
それが、「一般社団法人おらが大槌夢広場」であった。
早速、当方の訪問日時を伝え、ガイドの申し込みを希望した。
東梅さんは、高校の卒業時に「あの日」に遭ったそうだ。
あれから、3年余りの時間が過ぎて21~22歳の青年になるが、彼の一言一句は、頭頂部から足の指の爪先までズドンと落ち響く「言霊」であった。
どの場所に立っても、彼が繰り返し話してくれたことは、「自分の命は自分で守る」、「日頃から大切な人を大事にする」ということであった。
いま大槌町は復興に向けた工事が進められ、ダンプカーが忙しく土砂を運んでいた。
旧役場庁舎も、一部が保存されるそうだが、解体に向けた足場が架けられようとしていた。
こうした遺構の1つ1つの保存についても、町民の間で何度も議論されたが、賛否はほぼ半々。
1人1人にとって、「忘れてはならない時間」と、「忘れたい時間」があり、特に後者の方々にとっては、見るとどうしても思い出して辛くなるという心情が強いとのことだった。
また、町全体が嵩(かさ)上げされてゆく中で、消えつつあるものを東梅さんは案内してくれた。
旧庁舎から歩いて3分ほどの場所、ここはかつて町の中心部で多くの商店や家屋があったという。
いまはそれらがあったことを、辛うじてうかがい知ることができる、コンクリートの基礎部分があった。
そして、ある御宅の基礎が残る歩道部分には、このような文字が遺されていた。
「どこにいだの みんなまってるよ!」
"どこにいだの"は、どこにいるの?という、この土地の言葉…
青いペンキで書かれたこの文字は、津波で離れ離れになった家族が、自宅のあった場所に必ず戻ってくる、戻ってきてほしいという願いを込めた、命や絆を繋ぎとめたる文字であった。
「いま みなさんは そうした場所に 立っているのです」
「みなさんが それぞれ ここで何かを 感じてください」
「そして その感じたものを いつまでも 大切にしてください」
東梅さんは、再びそう話してくれた。
続けて、この文字もやがて嵩上げ工事に伴い、なくなります…と。
一方、大槌町住民の中には、私どものように被災箇所をガイドする姿を、快く思っていない人も少なくないと説明してくれた。
それは、「見せ物じゃない」という、強い意識。
しかしながら、東梅さんは、自分も当初はそう思っていたが、大槌町が本当の意味で復興できるのは、この大震災で多くの尊い命と引き換えに得た教訓を、自分たちが他の人々に伝えることだと悟り、この職業に就いたと話してくれた。
多くの人々の命や平穏な暮らしを奪った甚大な災害で、後世に伝えるべき反省や教訓、戒めは何であったのか…
テレビや新聞の画像、字面(じづら)だけでは、わからない、伝わりきらない、「何か」が、車掌長の胸に落ちた。
末筆ながら、東梅さんに心からお礼申し上げます。
ありがとうございました
余市蒸留所(哲×鉄車掌区慰安旅行)
カテゴリー:③番線:時間旅行、時刻表方面 2014年9月 6日 05:09
来道4日目。ニセコで迎えた朝は爽やかであった。
ニセコのシンボル、蝦夷富士こと「羊蹄山」には雲がかかっていた。
日差しは強かったが、空気は乾燥し気温は18℃。普通の人にはもう一枚ほしいかも…
予報を見れば、お天気もまずまずのようだ。
今日はニッカウヰスキー余市蒸留所を訪れる予定だったので、ひと安心。
余市蒸留所は8年前、たくちゃんさん夫婦が訪れた際の話を聞いて以来、訪れたかった場所…
ニセコからは車で1時間ほどで到着。ちょうどガイドツアーに間に合うタイミングであったが、車掌見習もいるので、自分たちのペースで歩ける「フリーコース」で受付をした。
広い敷地に歴史を感じさせる建造物が整然と並ぶ光景に胸が躍る。
竹鶴政孝が夫人リタとともに、「日本のスコットランド」を夢見て、生涯をかけた北の大地…
そして、世界唯一の「石炭直火焚蒸留」を継承する昔ながらの製法に、竹鶴政孝の描いたウイスキーづくりへの理想と情熱に想いを馳せてみたかった…
ニッカウヰスキーは1934年7月2日、「大日本果汁株式会社」として設立。
今年が創業80周年となる節目となり、ぜひこの機会に訪れたいと考えていた。
昭和9年という時代に、竹鶴政孝が「日本人に本物のウイスキーを飲んでもらいたい」という、ただそれだけの想いを胸に抱き、それだけに生涯を捧げた人物の「時間旅行」を、ほんの断片でも共感したいと思った。
ところで、「NIKKA」と言えば"髭オジサン"と言えるほど、トレードマークにもなっている「キング・オブ・ブレンダーズ」を思い浮かべる。
札幌の歓楽街すすきの交差点に、堂々たる風格の電飾看板を目にした人も多いであろう。
幾つもの香りを利き分けるというその御方に、ウイスキー博物館に入ってすぐお会いできた。
子どもの頃、家にあったウイスキー瓶の主に会え、思わず一礼してしまった。
ウイスキー博物館の展示物は、もっとじっくり時間をかけて見たかったが、専務車掌と交替で車掌見習の相手もせねばならず、またの機会とした。
博物館見学後、車掌見習は借りたベビーカーで眠り始め、再び敷地内を散策。
見学用に開放している一号貯蔵庫内には、整然と空樽が並べられていた。
空樽とは言っても、原酒の芳醇な香りが外まで漂い、心地よい場所であった。
ウイスキーの原酒が増えるごとに、貯蔵庫の数も増えて、現在では26棟あるという。
それらの庫内では、ウイスキーが熟成の「時」を静かに重ねていることを想像すると、車掌長の「時」に対する感性が満たされ、ささやかな幸せに包まれた。
おそらく自分自身がこの世にいない頃に、誰かの喉を潤す原酒も、きっとこの中にあるのだろう…
ふと、90年カセットテープに例えた自身の人生が、B面に入ったことを思い出してしまった。
一通り見学し、最後の楽しみは「原酒」を買うことであった。
原酒は、単一の樽から直接ボトリングされたモルトウイスキー。
蒸留所では、様々な個性のモルトウイスキーを創り出すため、樽の材質や使用回数、焼き方、サイズを変えて貯蔵するそうだが、これこそが樽ごとに唯一無二の原酒を生み出す魅力だと思う。
しかしながら、この原酒販売は大人気で、売店に残っていたのは「5年」のみ。
10年、15年は完売で、次回の入荷時期は数週間先とのことであった。
せっかくなので「5年」を購入。樽番号は407617。
一期一会の琥珀色の浪漫にとりつかれた車掌長は、早く自宅に戻って香りや味を楽しみたい衝動に駆られた。
また、もうひとつ余市蒸留所限定販売の「余市12年・ピーティ&ソルティ」のミニボトルを購入した。
名前から潮の香りを連想し、スコットランドのアイラ島のシングルモルトウイスキーと似ているのかなぁ…などと期待を膨らませた。
午後は、再び連泊となるニセコへ戻って、牧場で車掌見習の自由時間。
デコボコの牧草地を歩き回ったり、トラクターに牽いてもらう馬車のような面白い乗り物遊びに興じた。
明日は、のんびりと新千歳空港へ向かい、東京へ帰るだけの日。
これで、今夏の哲×鉄車掌区慰安旅行の雑多な記録は終わりにしたい。
コメント(2件)
たくちゃんさんからのコメント(2014年9月 8日 07:06投稿)
ずいぶんと久しぶりの乗車になります。
皆様、お元気でいらっしゃいますでしょうか?
ここ最近も、保線担当は、相変わらずの開店休業状態でございます。
トラブルがないということは、実に良いことです。
さて、今回は、ワタクシたちのつたない思い出話にも触れていただき
まことにありがとうございました。
当時の風景が懐かしく思い出されました。
Peaty and Solty をご購入とのこと。
いや、実にうらやましい。
ワタクシが購入いたしましたのはSoft and Dryでしたが
当然、そちらは既に手元にはございませんでね。
ワタクシたちの胃袋に、思い出と共に健全に納まっておりますよ。
最近は、余りの生活の大変さに、
あのころのように流離っておりません。
流離うことに憧れを抱きつつ、日々のよしなしごとに終われる毎日でございますよ。
随分、お会いしていませんね。
何とかワタクシたちも時間を作りたいと思っておりますが
現状の状況を打破しないことには、なかなか難しいです。
そのために、多少のお金もかけて、いろいろやっておるんでございますが、
すぐに結果に反映されるものでもございません。
とにかく頑張って、少しでも早く、
皆さんと以前のような生活ができるよう
日々、乗り切ってまいりますよ。
私たちは、なんとか元気です。
皆さんも、お身体ご自愛ください。
車掌長さんからのコメント(2014年9月 9日 21:35投稿)
たくちゃん 様
久々のご乗車ありがとうございます
日々のたゆまない保線のおかげで、哲×鉄も無事運行できること、心から感謝しております。
この場を借りて、そのご尽力に敬服しますとともに、お礼申し上げます。
念願の余市にも、この度やっと訪れることができ、たくちゃんさんの感動を追体験できた感慨に耽っております…
あそこでしか、手に入れることのできない価値のある「味」に感動しました。
ぜひ、いつの日か、小樽あたりに宿をとり、お互いにドライバーとしてではなく、列車で余市を訪れ、あれこれ試飲を楽しみたいものですネ。
具体的な当てがなくとも、何か先の「楽しみ」をもつことや、「夢」を見ることは、日々の生活に潤いを与えてくれるものと感じます。
また、どんなにか、しんどい時期があっても、そんな当てのない楽しみがあれば、踏ん張れるような気もします。
車掌長は、以前、そのような「楽しみ」さえ持てぬほど、見失うほどに、自分なりの絶望の淵に陥った時期がありました。
絶望の淵とは言っても、その概念や基準は、人それぞれであり、世の中には、客観的にもっと過酷な境遇の人が存在することも、重々承知しています。
しかしながら、あるきっかけで、そんな車掌長なりの絶望の淵から這い上がる手をさしのべてくれる人がいて、ほぼ同じようなタイミングで、たくちゃんさんご夫婦との縁も深まったことを、無上の喜びに感じています…
そして、そんな御縁の延長線上に、この「哲×鉄」誕生の縁も由来もあったのだと信じております…
たしかに、いまは仰る通り、大変な時期かとお察しします。
具体的な手助けがなかなかできないことも、歯痒さがありますが、たくちゃんさんの持ち前のセンスや、仕事に対する責任感、こだわり、情熱が報われることを、誰よりも願ってやみません…
ぜひ、少しでも報われたときは、そちらでも、東京でも構いませんので、祝杯しましょう!
大奮発して「函館」での祝杯も、オツかもしれません。
末筆ながら、たくちゃんさんもお体には、くれぐれも気を付けて…
2件のコメントがあります → まだまだコメントお待ちしてます!