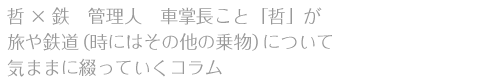黄昏 最終話
カテゴリー:⑬番線:臨時寝台特急北斗星 2015年12月26日 05:55
♪友達と呼び合う仲がいつか
知らぬ間に それ以上のぞんでた
霧積と手白沢の出逢いは、3年前の夏…
手白沢が高二の夏休み、クラスメイト4人で神州を訪れたとき。
ユースホステル(YH)という、若年の旅行には心強い廉価で泊れる宿でのこと。
一人旅の霧積に、手白沢が声をかけ「旅」の話をしばらくしていた。
夕食の時間が近づいた頃、霧積は一片の小さな白い紙に何かを書きはじめ、手白沢に渡した。
その小片に目をやると、名前と住所、誕生日が書かれてあった。
誕生日を見て1つ年下であることがわかった。
可憐だ…
手白沢は胸の内で、そう呟いた。
互いにアドレスを交換し、それぞれの旅も終わった。
そんな或る日、手白沢の家の郵便受けに可愛い封書が届いた。
宛名の見覚えのある字にときめき封筒を裏返すと、霧積の名前が書かれてあった。
開封した便箋には、YHで別れた後の霧積が訪れた場所や感想が記されていた。
手白沢はそれを追体験するように、乗った列車やバスを時刻表でなぞってみた。
その手紙がきっかけとなり、二人の間で文通が始まった。
ひと月に2~3往復ほどのペースで、手白沢は学校から帰る時間が早くなった。
そして、郵便受けを覗いたときに、期待する人から届く封筒が楽しみでならなかった。
初秋の手紙の中に、霧積の通う高校の文化祭の招待券が同封されていた。
某県でも有数の進学校で女子高であった。
立派なプラタナスの木が、気高く空に向かって枝を伸ばしていた。
中秋の頃、今度は手白沢が霧積を文化際に誘った。
招待券など洒落たものはなく、ただ当日来れば良い、某都でも有数の自由奔放な男子校であった。
とても狭い校庭だが、真紅の某都タワーが間近に見えた。
年の瀬も押し迫ったクリスマスの頃、手白沢は霧積の住む街を訪れた。
手白沢が文通の中で、霧積の住む街に興味を持ち色々尋ねたら、来たら直接案内してあげると返事があり、1ヶ月ほど前からその日を心待ちにしていた。
待ち合わせは、霧積の自宅の最寄駅。
そこに朝7時半となった。
小さな駅だからすぐわかると書かれていた。
待ち合わせの時間から逆算すると、手白沢は自宅最寄駅から出る始発の地下鉄に乗り、途中3回乗り換えて間に合う土地だった。
電車の中で夜が明け、広い平野にも山が見え始めた。
駅に着きホームに降り立つと、手白沢の住む街とは違う冷たい空気に、ふと、見えないはずの透明感が目に映り、クリスタルな匂いを嗅ぎ分けた。
時計をみると、待ち合わせには少し時間があり、なるほど改札口は1つしかなく、迷うことはないと納得した。
それにしても、かなり寒い…
そんなとき、背後からふわりとした感触が首の辺りを包んでくれた。
「こっちは寒いでしょ!?」
霧積の弾む声がした
「これ、編んだの…良かったら使って!」
霧積はひと月余りかけて、手編みのセーターをこしらえてくれた。
勉強の合間に少しずつ編んでくれたそうだ。
歩き始めると、霧積は自転車で来たと言う。
冬の早朝に白い息を吐きながら…
ふたりの間には自転車が介在する形となったが、それは気持のクッションのような役割も果たしてくれた。
手紙に綴られていた、近所の有名な御宮で手を合わせたり、「からっかぜ」という冬場に吹く強風は、あの山の向こうから来るなどという話を聞きながら、霧積の自宅に到着した。
玄関では霧積の母上が出迎えてくれ、恐縮しながら挨拶すると、
「マフラー似合うわね!毎晩遅くまで編んでたみたいヨ」と気さくに笑いながら話してくれた。
母上お手製の三色弁当を頂き、午後は手白沢の希望で近くを走る国鉄のローカル線に乗った。
冬枯れの山々を渓流に寄り添いながら縫って走るような路線だった。
2両の気動車は、途中から終着駅まで霧積と手白沢だけとなった。
車内は心地良い暖房と穏やかな陽光も差し込み、さながらこのまま天国にでも行ってしまうのではないか…と思われるほど、至福な時間が過ぎた。
折り返した列車は、日も暮れた現実のホームに滑り込んだ。
「こんど会えるのはいつだろうね」と交わし合った会話に、明確な答えはないまま別れた。
その後、受験勉強を理由に文通は途切れた。
ただ、1度だけ一足先に大学へ進学した手白沢は、その転居先だけを知らせる葉書を出した。
返事はなかった。
あの日から3年が過ぎ、ふと、夕闇の夏の海に佇む我に戻った手白沢は、その日から今日に至った時の調べを回想していた。
そして、不意に鳴った3日前の電話は、過去と現在の時間を一瞬で結びつけた。
いまこの浜辺で肩を寄せ合うふたりに、甘美な夢の続きのような時が流れ始めた…
♪ああ 恋する想いはなぜかいつも
少しだけ まわり道ね
ああ このままこの手を離さないで
さまよう トワイライト・アヴェニュー
おしまい
黄昏(前略:北斗星よ永遠に)
カテゴリー:⑬番線:臨時寝台特急北斗星 2015年8月23日 09:25
本日の哲×鉄トップページにご注目いただきたい。
乗務日誌の更新情報には、「2015年8月23日、13番線、臨時寝台特急北斗星、9:25着」の表示がある。
これは、本日同刻の上野駅13番線到着をもって営業運転を終了した「北斗星」への、万感の想いを込めた記録の一助だ。
1958年、日本初のブルートレイン「あさかぜ」誕生から、わずか57年弱という短い歴史に幕を降ろしたことを無念に思う。
今後は、想い出の中を走り続ける「北斗星」として、哲×鉄ブログ本線「乗務日誌」において、臨時寝台特急として走らせ続けたい。
以下、第3話となった「黄昏」を続けたい。
(ただいま停車中)
黄昏 第2話
カテゴリー:⑬番線:臨時寝台特急北斗星 2015年7月26日 14:30
今日のドライブは、3日前の電話がきっかけだった。
彼はハンドルを握りながら、この日に至るまでの楽しい時間を遡っていた。
彼が住む学生用アパートには、共用のピンク電話が設置されていた。
その建屋は2階構造で、住人は両階とも4人で計8人。
電話は1階屋外廊下の2号室と3号室の前辺りに置かれていた。
電話が鳴れば、誰かが出て取り次ぐのが、管理人である大家さんから言われたルール。
しかしながら、誰もが真っ先には出ないのが、住人たちの暗黙の了解でもあった。
なぜなら、自分宛の電話に当たる確率は8分の1…
つまり、単純な確率では、ほとんどが自分以外の電話となる。
実態としては、30回ほどベルが鳴り続ければ、1階の誰かが渋々出ることが多かった。
そして、その日もベルが30回以上鳴り、1号室住人の彼が面倒くさそうに無言で電話に出た。
「もしもし?…夜分にすみません。手白沢さんお願いしたいんですが…」
彼には聞き覚えのある声だった。
「あっ、俺だけど…誰?」
彼は9割9分、彼女とわかっていながら聞き返した。
「あっ、良かった!霧積です!」
「なんか、初めてかけてみたんだけど、だいぶ鳴らしたのに誰も出ないから、間違えちゃったかと思って…あと1回鳴らしたら切ろうと思ってたの」
言葉に曇りのない彼女の話し声は、夏の夜風に吹かれながら聞く心地良さがあった。
「わるいね、広い家だから電話まで遠いんだヨ」
「それより、どうしたの?電話をくれるなんて初めてじゃない?」
彼は突然の電話に不安と期待の入り混じった心持ちで訊ねてみた。
「うん、今度の日曜にね、そっちの方に行くから、会えたらいいな…と思って」
彼女の顔はもちろん見えないが、はにかむ様子が声からわかった。
「今度の日曜?! 午後まで仕事だけど、その後でも大丈夫なら…」
彼は内心嬉しくも、平静を装いながらそう返答し、こう付け加えた。
「じゃ、今度の日曜16時に、"南ならば駅"で待ってるヨ」と。
「良かった!じゃ、例のアレも持ってきてネ!」
彼女は無邪気に言いながら、屈託なく電話を切った。
二人を乗せた車は、例のアレから流れる想い出の曲を1つ1つ聴きながら走り続けた。
やがて、車は国道沿いの小さな灯台の前にある店の駐車場に停まった。
夕闇の中で白亜の灯台が、彼の目にひときわ白く映った。
♪逢わないでいられるよな恋なら 半分も気楽に暮らせるね
彼は心の中でトワイライトアヴェニューの歌詞を、そう口ずさんだ。
つづく
黄昏
カテゴリー:⑬番線:臨時寝台特急北斗星 2015年7月 4日 05:42
「これ、なんて曲?!」
彼女が助手席で声を弾ませる
車は対面通行の国道742号線を、颯爽と走っていた。
喜多半島を時計回りにドライブ
南端の岬で折り返し北上すると
左手に海がぐっと近づいた
「これ? トワイライトアヴェニューさ」
彼は聞かれたことだけを答え、微笑んだ
彼女は運転する彼の聞き慣れた声に、安堵した
陽も沈みかける黄昏時…
夕映えの中、ハンドルを握る彼の横顔がシルエットとなり浮かび上がっていた…
寄せては返す穏やかな波も、逆光を浴びキラキラ輝いている
魔法でもかけられたような美しい光景は、この曲のイントロそのものであった
まるで超微粒のダイヤモンドを、あどけなく手から海に撒いたかのよう…
心地良い時の流れは、いまの彼女の心とシンクロナイズ
カーステレオから流れるmelodyが、彼女の耳から離れられなくなった
♪あぁ あなたに ときめく心のまま 人知れず 寄り添いたい
つづく